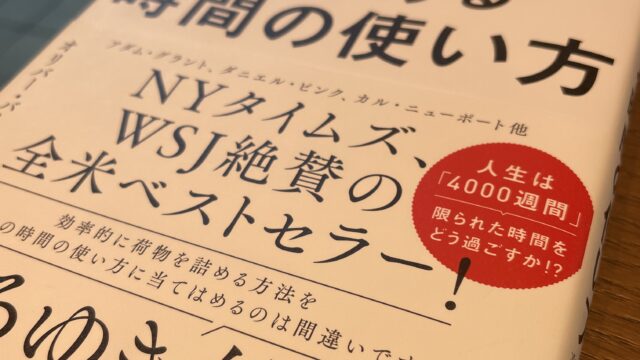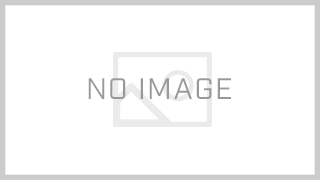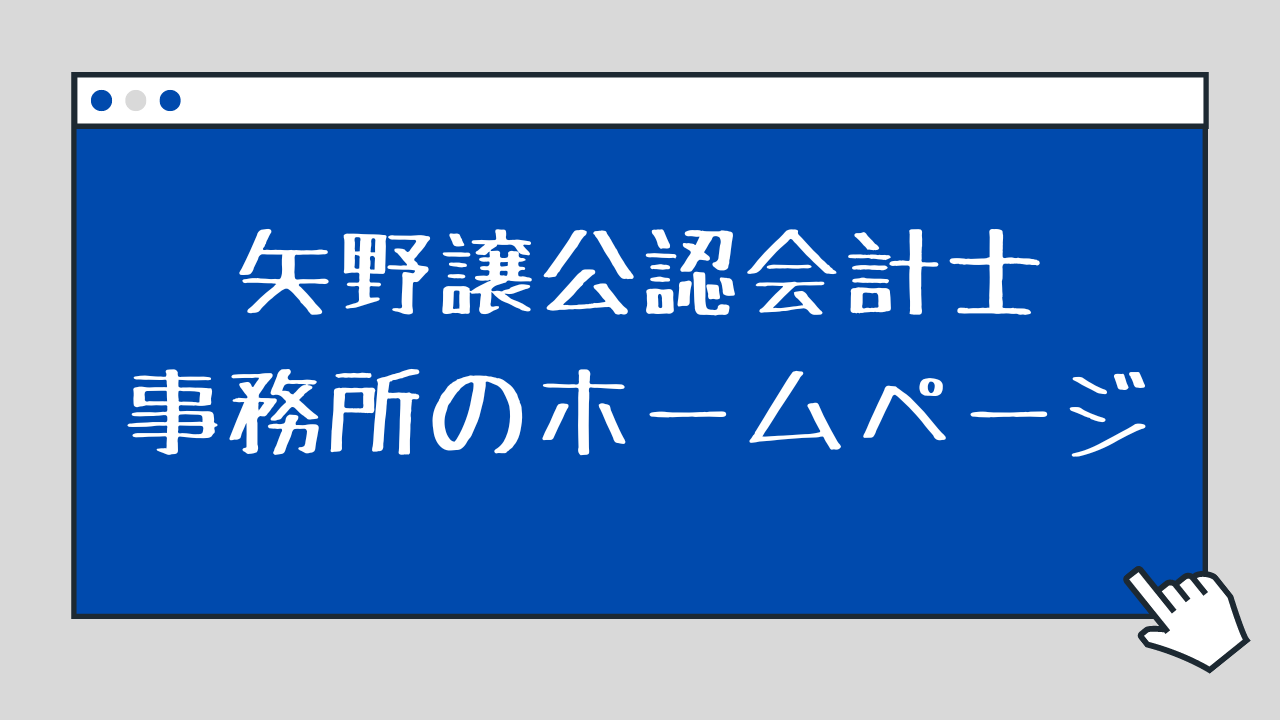スポンサーリンク
ミステリーであり、かつ、壮大なドラマだった。
ここまで気持ちが抉られる作品は久しぶりだ。
ネタバレあるので、未読の方はここまで。
それでも生きていて欲しいと思った。読後、辻村深月の解説を読んで、それでもなおそう思った。
著者はどんな思いでこの作品を、幸乃の最期を書いたのだろうか。私が知らない絶望を、どれだけ知り、理解して、それを投影したのだろうか。
私は後半、慎一視点で物語を見て、そしてそこに自分を投影しながら読んでいたと思う。だからこそ最後には絶望感でいっぱいになりそうだった。残りの人生を自責と悔恨で埋め尽くすことになるだろうと思う。
そして幸乃の人生。いくつかの分岐点で考え得る限り最悪の道を進まざるを得なかった彼女に、自分を重ねることさえできない悪辣なその道に、こんな人生があり得るものなのか、目を背けあり得ないと信じたい欲求に駆られる。事実、現実にはあり得ないのかもしれないが、そこには確かに存在していた。
彼女の人生を描くことで作者が伝えたいメッセージはなんだったのだろうか。今はまだそれを冷静に考えることは難しい。いや、難しいどころか皆目検討もついていない。今は何も希望を見出せていない。それでもいつかわかる日がくるのだろうか。
今はただ思いを馳せることしかやれることがない。だから、寝る前に時々思い出してはまだモノトーンなイメージしかわかないこの作品に色をつけていけたらいいなと思う。それがきっと桜色なんだろうということだけが確かなこととして。
スポンサーリンク
スポンサーリンク